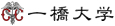講演会・セミナー
- トップ
- 魅惑の世紀末 第4回ロダン “考える人”から考える
魅惑の世紀末 第4回ロダン “考える人”から考える
第95期一橋フォーラム21 魅惑の世紀末
第4回「ロダン 没後100年“考える人”から考える」
開催日 2017年11月27日(火)
開場 16:00 *如水会館1Fレストランマーキュリーの12%割引券をお渡しします。
時間 18:30~20:00(18:15よりピアノの演奏を行います)
会場 如水会館2F オリオンルーム
講師 日本大学芸術学部 教授 髙橋 幸次
■講演要旨
オーギュスト・ロダン(Fran ois Auguste Ren Rodin, パリ1840-1917パリ)は19世紀フランスを代表する彫刻家ですが、本年で歿後100年を迎えました。代表作《考える人》(1880年、拡大像1902-04年)はあまりにも有名で、作者ロダンの名を知らずとも、この作品を知っている人は多く、また、そのポーズや雰囲気のイメージは広く記憶されています。歴史上著名な名品はいくつもありますが、近代の作品でこれほど流布されたものは珍しいと言ってもよいでしょう。
「考える人は何を考えているのか」という質問もよく受けます。拡大された単独像の《考える人》では曖昧なこの意味もまず本来の場所《地獄の門》(1880-90年頃)に立ち返ると得られます。そして単独像の意味も浮かび上がってきます。
元来《考える人》は《地獄の門》の中心とも、要石とも言える場所、主宰者の位置にいました。「ダンテ」、「詩人」とも呼ばれていました。ここで眼下に地獄の光景を見ている、あるいは目を閉じて彼の頭の中に広がる光景が地獄なのです。構想の発端となったダンテの『神曲 地獄篇』の導き手の詩人ウェルギリウスもおらず、彼はただ一人で座って瞑想しています。行動の前の思考というよりは、地獄の光景に手も足も出ずに、黙然と座しています。故アルバート・E・エルセン氏は「ロダンは自分の公私にわたって職業に讃辞を与えており、《地獄の門》のなかにあって、《考える人》は芸術家であり、芸術と生活について考えている」とまず結論付けています(Elsen, Rodin’s Thinker… 1985, p.71)。
しかしその後、この芸術家像も、単独像そして拡大像として展示され、ついには1906年にパリのパンテオン前に設置されたことによって、その意味も変わります。時代は世紀末から世紀をまたぎます。募金によって鋳造、設置されたこの像は、人間の知的活動の象徴となったのです。独立拡大されて、「ヘラクレス」と称された大きな体躯が強調され、行動的知性ともいうべき積極的な意味を与えられたのも、当時の人々のアイデンティティを代弁するものとされたからでしょう。しかしもちろん賛否両論がありました。広く言ってロマン主義的な思潮から世紀末に向かって、ここに苦悩や宿命、美と死、爛熟退廃や諦念といった同時代認識を読むこともできました。そうした時代感覚からの時代限定的な解釈もあります。しかし《考える人》はそこにとどまらず現代にも訴える時代超越的で普遍的な力を持っています。
そうした意味に加えて、捻り螺旋構造、持ち送り構造、量塊、動勢、強調、バランスといった、人体像という彫刻の内的・外的な力学的構造や造形要素が、実は、この像の強い印象を決定づけているのです。人々の記憶に残るには、ポーズや意味以上に、彫刻の構造の秘密があるのです。
そして実はロダンにとって、パリに記念像として公的に設置されたのは、この《考える人》が最初だったという事実も驚きです。美術学校不合格、サロンやコンクール落選、スキャンダル、作品完成の遅延や受け取り拒否といった苦節を経て、1889年のモネとの2人展、1900年パリ万博時に同時開催した大回顧展で名声を確立したロダンは、世紀末前後の「象徴性」を背景に、1906年《考える人》の設置によって、19世紀芸術に不動の地位を築いたのです。成功は世紀末にやってきたのです。
ところで、《地獄の門》は建設計画が持ち上がっていたパリの国立装飾美術館のための扉を、ロダンが受注したものですが、美術館建設そのものも立ち消えとなり、代わりにオルセー駅(現オルセー美術館)になってしまい、ロダン自身も《地獄の門》を未完成のまま世を去りました。
また、《バルザック像》は文芸家協会から依頼された肖像彫刻でしたが、制作は遅延し、サロン発表時には協会から受け取り拒否となりました。ロダンはこれを引き取り、この像の正しさを確信していましたが、石膏像のままで死去しました。この像がパリの街角に設置されたのは1939年になってからです。ロダンはここでも「象徴性」への昇華を辿って、さらにその普遍性は20世紀アートに少なからぬ影響を与えたのです。
ロダンの代表作、中期の《考える人》(1880年)から始めて、未完の大作《地獄の門》(1880-90年頃)を経て、後期の《バルザック像》(1891-98年)へ、そして晩年の拡大された《考える人》(1902-04年)に戻り、世紀末のロダンの実現した「象徴性」の力を考えます。同時に、ロダンの人となり、作品の展開、その影響とその後についてもお話ししたいと思います。